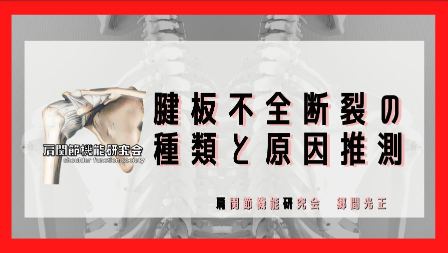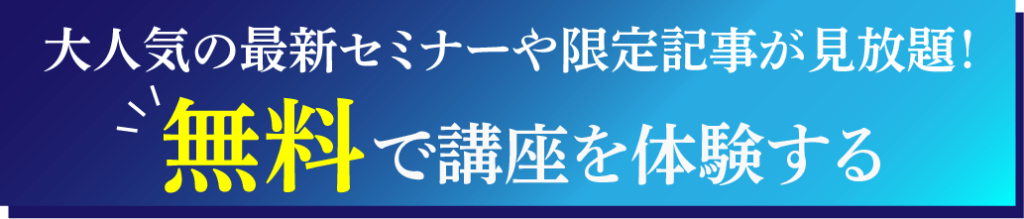今なら有料セミナー・有料記事が一週間無料で体験できる!
↓登録はこちら↓
![]()
こんにちは。
肩関節機能研究会の郷間(@FujikataGoma)です。
今回は”腱板断裂不全断裂の種類と原因推測”というテーマでお話していきたいと思います。
そうです。
100%ではありませんが、不全断裂の種類(タイプ)から、症例がどのような経過で断裂に至ったのか?といった推測をすることが可能です。
特に理学療法士は機能を改善することが主な仕事のため、腱板断裂の”原因”を理解する必要があり、また理解することができれば”解決策のヒント”も見つかるかもしれません✨
そのため、本記事は
✅普段から保存、術後腱板断裂患者を担当する
✅腱板不全断裂の種類(タイプ)を詳しく知らない
✅種類(タイプ)はなんとなく知っているけど、そこから考察をしたことはない
これら3つの項目に該当するセラピストにはぜひ読んでいただきたい内容となっております。
本記事は3~5分ほどで読み切ることができますので、ぜひ最後まで読んでみてください(^-^)
![]()
郷間
種類を知ることで、臨床の疑問も解決しやすくなるのでぜひ覚えてください✨
腱板不全断裂の種類
![]()
腱板断裂は大きく分けて全層断裂と不全断裂(部分断裂)の2種類あります。
全層断裂に関してはこちらのリンクからご一読ください✨
➡リンク ※調整中
では、今回の本題である不全断裂をもう少し分解してみてみましょう。
不全断裂は大きく分けて3種類に分類することができます。
腱板不全断裂の種類
1.滑液包面断裂(Bursal-sided tears:BST)
2.関節面断裂(Articular-sided tears:AST)
3.腱内断裂or層間剥離(Delamination)
ではそれぞれの不全断裂にはどのような特徴があるのでしょうか?
今回は腱板=棘上筋として解説していきます。
1.滑液包面断裂(Bursal-sided tears:BST)とは?
まずは滑液包面断裂(以下:BST)から確認していきましょう。
BSTは文字通り肩峰下滑液包側の腱板断裂です。
棘上筋は深層線維と浅層線維に分けることができ、肩峰下滑液包側の棘上筋は棘上筋浅層線維にあたります。
したがって、BST=棘上筋浅層断裂となることがわかってきます。
ではBSTはどのようにして生じることが多いのでしょうか?
一般的に言われているのは、肩挙上時に上腕骨頭が上方に変位して生じる肩峰下インピンジメントが原因であると言われています。
また、BSTの場合は断裂部(断端部)がめくれあがったり腫脹することで痛みが生じることがあります。
この断裂部の腫脹のことを断端腫脹といいます。
断端腫脹は肩峰と腫脹した断端がひっかかることで肩峰下滑液包炎などが生じやすく、安静時痛、動作時痛、夜間時痛などが生じやすいのでしっかり頭に入れておきましょう。(結構厄介です。)
2.関節面断裂(Articular-sided tears:AST)
次に関節面断裂(以下:AST)を確認していきましょう。
ASTは文字通り関節窩と上腕骨より形成される肩甲上腕関節面側の腱板断裂です。
先ほど述べたように棘上筋は深層線維と浅層線維に分けることができ、関節面側の棘上筋は棘上筋深層線維にあたります。
したがって、AST=棘上筋深層断裂となることがわかってきます。
ではASTはどのようにして生じることが多いのでしょうか?
一般的に言われているのは、外傷など強い衝撃により過度な挙上が生じる際に生じるインターナルインピンジメントが原因であると言われています。
また、ASTの場合はBST(滑液包面断裂)と違い断端腫脹が生じにくい断裂です。
ひとりごと
個人的な見解ですが、理学療法を行う際、ASTの方が比較的経過がスムーズに進み、BSTの方が可動域制限や痛みは残存しやすい印象です。
おそらくASTもBSTも器質的な破綻ではありますが、ASTの方が外傷であり、長い間肩峰下インピンジメントを繰り返していたBSTの方が機能的に改善が必要なことが、このような経過の差を生んでいるのではないか?と考えています。
3.腱内断裂or層間剥離(Delamination)
では最後に腱内断裂or層間剥離(以下:デラミネ)を確認していきましょう。
デラミネはASTやBSTと違い、棘上筋の深層と浅層間で筋が剥離してしまった状態の腱板断裂です。
このデラミネに関しましては、発生機序が未だ明確ではなく、一定の見解を得られていないのが現状です。
しかし、いくつかの報告では関節鏡視下腱板縫合術後の再断裂の因子になり得るという報告もあります。
私達セラピストが直接かかわるポイントはありませんが、言葉とその意味だけでも覚えてしまいましょう(^-^)ノ✨
なぜ腱板断裂は修復術をするのか?普通の肉離れとは違うのか?
一般的な肉離れなどでは筋腹内の断裂、筋腱移行部の断裂、腱と骨の付着部断裂などがあります。
筋腹内の断裂は血管栄養も豊富のため、比較的修復が早いのですが、筋腱移行部は筋腹内の断裂と比較して血管栄養が少なく、修復しにくい部位となっています。
そして、腱板損傷は筋と筋の肉離れではなく、腱と骨で剥離している状態のため、血管栄養が乏しく自己修復しにくい断裂となっています。
このような理由からも腱板断裂後に腱板縫合術が広く一般的に行われるのも理解ができますね。
肩関節、腱板断裂をみる場合はぜひ断裂の種類も一緒に覚えてしまいましょう(^-^)ノ✨
ということで、本記事はこのあたりで締めたいと思います。
これからも一緒に研鑽していきましょう!!
今後も皆さんに有益な情報がお届けできるよう尽力いたします!
以上、肩関節機能研究会の郷間からでしたっ(^-^)ノ
まとめ
・腱板断裂には全層断裂と不全断裂に分けられる。
・不全断裂はそこから滑液包面断裂、関節面断裂、腱内断裂(層間剥離)に分けられる。
・それぞれの断裂タイプを知ることで、次の臨床で問題点の抽出がスムーズになる。
今なら有料セミナー・有料記事が一週間無料で体験できる!
↓登録はこちら↓
![]()